2025年10月23日
【50代からの不動産投資】出口戦略と資産承継のポイントを徹底解説
50代以降は老後資金や相続を現実的に意識し始めるタイミングであり、不動産投資においても「買う」より「どう活かすか」「どう引き継ぐか」という視点が重要になってきます。
そのため、これまで長期にわたって築いてきた資産をどのように維持・運用・承継していくかを考えることが、これからの不動産戦略の中心です。
この記事では、50代以降に押さえておきたい出口戦略と相続対策の基本を整理しつつ、安定した資産管理とスムーズな承継を実現するためのポイントを解説していきます。
50代以降の不動産投資における目的とは
収益よりも「安定性」を重視する段階へ
50代以降の不動産投資は、20代〜40代のように積極的な拡大を目指すフェーズではありません。
今後は「安定した収益を維持しながら資産を守る」ことが主な目的となり、長期保有してきた物件の収支を見直して修繕計画や借入残高の状況を整理しつつ、老後の安定運用に向けた移行を開始する時期です。
また新規購入を検討する場合も、高利回りを狙うよりは管理がしやすく賃貸需要が安定している物件を選ぶ方が現実的といえるでしょう。
家賃収入を“年金の補助”として位置づける
定年退職を控えた50代は、退職金や年金といった将来の収入がある程度見通せる段階に入ります。
不動産投資の家賃収入は、これらの収入とは別に「老後の生活費を補う定期収入」として活用する考え方が効果的です。
毎月安定して入ってくる家賃は、年金の不足分を補う“セーフティネット”となり、生活の安心感を高めてくれるでしょう。
現役時代のように大きく増やすのではなく、“働かなくても入ってくる収入源を確保する”という発想が重要です。
資産承継・相続を見据えた整理の時期
50代以降になると、将来の相続や資産承継を意識し始める方も多くなります。
不動産は現金と違い「形がある資産」であるため、分割や管理の方法をあらかじめ考えておく必要があります。
たとえば複数の物件を所有している場合、どの物件を売却しどれを残すのかを明確にしておくとよいでしょう。
また相続時の評価額を下げるために、賃貸中の物件を保有し続けるといった選択も有効です。
“運用から承継へ”と目的を切り替えることで、資産全体をより長く活かすことができるでしょう。
“出口戦略”を考えることの重要性
ゴールを決めておくことで“迷いのない運用”ができる
不動産投資は「購入したら終わり」ではなく、将来的にどのタイミングでどのように資産を手放すのかといった“出口”を設計しておくことが非常に重要です。
特に50代以降は、これまでのように20年・30年先を見据えて運用するのではなく、「10年後に売却して現金化する」「相続財産として残す」といったゴールを明確にしておくことで、迷いのない判断ができるようになるでしょう。
出口の設定は、資産を「増やす」ことから「どう活かすか」に視点を切り替えるための第一歩といえます。
売却を視野に入れた“資産価値の維持”がカギ
もし売却を想定しているのであれば、物件の資産価値を維持・向上させるための施策が欠かせません。
たとえば「外壁や共用部の修繕を定期的に行う」「入居者対応を丁寧に行う」「入居率を高く保つ」といった取り組みを積み重ねることで、売却の際に「高く・早く」売れる物件になっていくでしょう。
特に築年数が経過した物件は、管理状態の良し悪しが評価額に直結するため、修繕履歴や家賃履歴を整理しておくことが出口戦略の成功につながります。
相続・贈与を見据えた“出口の多様化”
出口戦略の選択肢は必ずしも「売る」ことだけではありません。
50代以降は、家族への贈与や相続といった「引き継ぎ(承継)」も現実的な選択肢のひとつとなります。
たとえば賃貸中の物件を保有したまま相続する場合、現金の状態で相続するよりも相続税評価額を下げられるため、節税効果を期待できます。
もし相続人が複数いる場合には、共有名義を避ける・法人を活用して承継するといった工夫によってトラブルを防ぐことができるでしょう。
安心して老後を迎えるためにも、「自分がいなくなったあと、資産がどう扱われるか」まで見据えて出口戦略を立てることが大切です。
相続税・贈与税対策としての不動産投資

不動産は“評価額を下げて“承継できる資産
不動産は、現金よりも相続税の評価額を下げられる可能性のある資産です。
たとえば現金1億円を相続すると評価額もそのまま1億円ですが、同じ1億円で購入した賃貸用不動産の場合、土地と建物の課税評価額が7,000万円程度まで下がるケースがあります。
さらに賃貸中の物件であれば、入居者の借家権分が控除され、評価額をさらに低くできることもあります。
このように「賃貸中の不動産を保有する=相続税評価額を圧縮できる」ことが、不動産投資の大きな魅力です。
贈与のタイミングを分散させて節税効果を最大化
不動産を子どもや配偶者に引き継ぐ際は「一度にまとめて」ではなく「計画的に分けて贈与する」ことがポイントです。
たとえば暦年贈与(年間110万円まで非課税)や住宅取得資金贈与の特例などを活用すれば、税負担を抑えながら少しずつ資産を移転することができます。
また贈与の際に不動産の一部持分だけを譲渡する方法を取ることで、相続開始時点での課税対象をさらに軽減することも可能です。
相続の準備は急に始めるものではなく、家族のライフステージに合わせて整えていくものと考えましょう。
相続トラブルを防ぐための「見える化」が大切
不動産は分けにくい資産であるため、相続時にトラブルが起こりやすい点には注意が必要です。
たとえば相続人が複数いる場合、1つの不動産を共有名義で相続してしまうと将来的に売却や管理の意思決定で揉める可能性があります。
これを防ぐためには、早い段階で相続人と話し合い「誰がどの資産を承継するか」を明確にしておくことが重要です。
また遺言書や財産目録を作成し、資産全体の分配方針を“見える化”しておくことで、家族間の不安や誤解を減らすことができるでしょう。
50代以降が注意すべきポイント
融資条件が厳しくなる点を意識する
50代以降になると、金融機関からの融資審査が徐々に厳しくなる傾向があります。
返済期間を長く設定できないことから月々の支払い額が大きくなりやすく、結果としてキャッシュフローを圧迫してしまうケースも少なくありません。
もし新規で物件を購入するのであれば、自己資金の割合を増やす・頭金を多めに入れるなどの“借入を抑えて安定を優先する”姿勢が重要です。
また長期ローンではなく短期返済型やリバースモーゲージ(自宅を担保に借入を行い、借入人の死亡時に担保不動産を売却することで返済する仕組み)など、年齢に応じた融資プランを利用することも検討しましょう。
修繕・管理コストの上昇を見越して備える
築年数が経過した物件では、修繕や管理にかかる費用が年々増えていきます。
特に50代以降のオーナーは、「引退後も継続して運用できるか」を念頭に置いて修繕積立金や管理委託費を再点検しておくことが欠かせません。
大規模修繕や入れ替え工事など、将来的に発生し得る費用をリスト化し、毎月の家賃収入から計画的に積み立てておくと安心です。
資産を整理して「持ちすぎリスク」を防ぐ
これまで築いてきた物件をそのまま抱え続けると、管理負担や税金面でのリスクが増すことがあります。
物件数が多い場合は稼働率や収益性を見直し、「残す物件」と「売却する物件」を整理しておくことが大切です。
特に老朽化が進んだ物件や収益性が低下している物件は、早めに売却して現金化することで将来の修繕リスクを減らせます。
資産を“増やす”だけでなく“適切に減らす・整える”視点を持つことが、50代以降の不動産投資を安定させる最大のポイントといえるでしょう。
50代以降の不動産投資【事例紹介】
事例①|50代後半・会社経営者のケース
- 現金資産:5,000万円
- 購入物件:賃貸中の一棟アパート(価格1億円)
- 資金計画:自己資金3,000万円+ローン7,000万円(金利2.0%/25年返済)
- 想定家賃収入:月83万円(年間996万円)
- 年間返済額:約360万円+管理・修繕費144万円
- 年間の収益:996万円-(360万円+144万円)=492万円
このケースでは、年間約490万円のキャッシュフローが見込めます。
経営者本人はすでに本業の収入が安定しており、老後資金というよりも「相続税対策」としての投資を重視しています。
この場合、現金で保有するよりも不動産として運用した方が相続時の評価額を約3割圧縮できるため、節税効果と安定収入の両立を実現できる手法といえるでしょう。
事例②|60代前半・定年退職者のケース
- 退職金+預金:3,000万円
- 購入物件:駅近の築浅区分マンション(価格3,000万円)
- 資金計画:全額キャッシュ購入
- 想定家賃収入:月12万円(年間144万円)
- 年間維持費:約24万円(管理費・修繕費・固定資産税)
- 年間の収益:144万円-24万円=120万円
このケースは、ローンを利用せずに安定的な家賃収入を得る「リスク最小化型」の投資方法です。
年金に加えて月10万円前後の家賃収入を得ることで、老後生活にゆとりを持たせながら資産を“現金以外の形”で保有することができます。
築浅・好立地の物件を選んでいるため、管理負担が少なく長期的な運用にも向いています。
資産を増やすというより、“守りながら活かす”姿勢を体現した事例といえるでしょう。
まとめ
- 50代以降の不動産投資は、収益拡大よりも「安定性」と「承継準備」を重視する段階に入る
- 出口戦略や相続対策を早めに設計することで、資産を守りながら次世代へ引き継ぎやすくなる
- 融資・修繕・管理などのリスクを見据え、無理のない範囲で資産を整理・最適化することが重要
老後や相続を見据えた不動産投資は、資産を“増やす”から“活かす”へと考え方を切り替える時期です。
安定した収入を維持しながら、家族の未来につながる資産運用を計画的に進めていきましょう。
会員限定情報
今だけのチャンスをお見逃しなく!
収支シミュレーションシート

関連記事
-
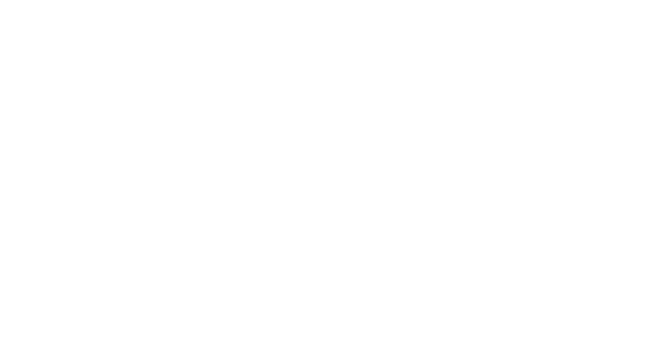 定期借地権の3つの種類とメリット・デメリットを初心者向けに解説2024-03-27不動産投資において、「定期借地権」は触れる機会が少ない権利です。しかし実際に出て......
定期借地権の3つの種類とメリット・デメリットを初心者向けに解説2024-03-27不動産投資において、「定期借地権」は触れる機会が少ない権利です。しかし実際に出て...... -
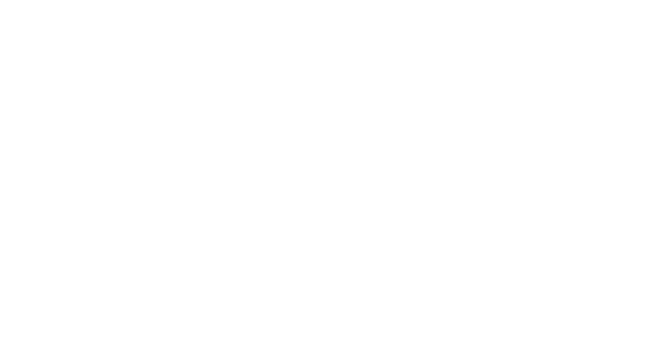 リノベーション投資とは?収益物件の選び方と工事のポイント・リスクを解説2024-03-27不動産投資初心者は、「入居者に好まれるオシャレな物件で賃貸経営をしたい」「デザイ......
リノベーション投資とは?収益物件の選び方と工事のポイント・リスクを解説2024-03-27不動産投資初心者は、「入居者に好まれるオシャレな物件で賃貸経営をしたい」「デザイ...... -
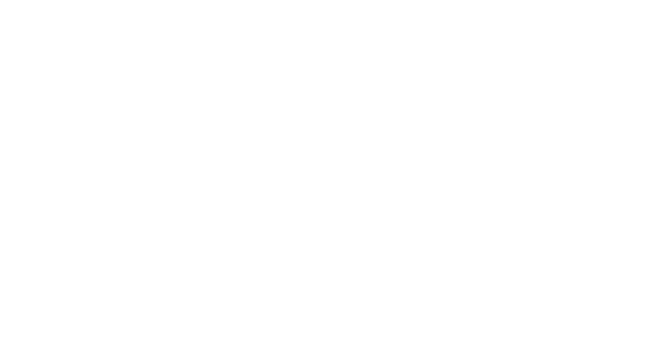 不動産投資でフルローンはできる?3つの事例からみるメリット・デメリット2024-09-29不動産投資を行う際に、フルローンを利用することで、頭金をほとんど用意することなく......
不動産投資でフルローンはできる?3つの事例からみるメリット・デメリット2024-09-29不動産投資を行う際に、フルローンを利用することで、頭金をほとんど用意することなく...... -
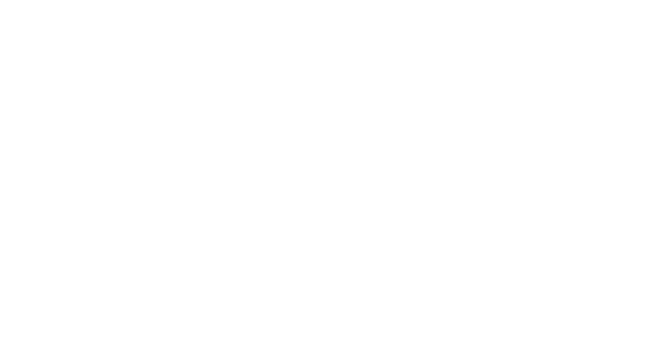 事業計画の種類とやり方をわかりやすく解説【動画あり】2024-03-28不動産投資で成功するためには、事前にしっかりと事業計画を立てることが重要です。計......
事業計画の種類とやり方をわかりやすく解説【動画あり】2024-03-28不動産投資で成功するためには、事前にしっかりと事業計画を立てることが重要です。計...... -
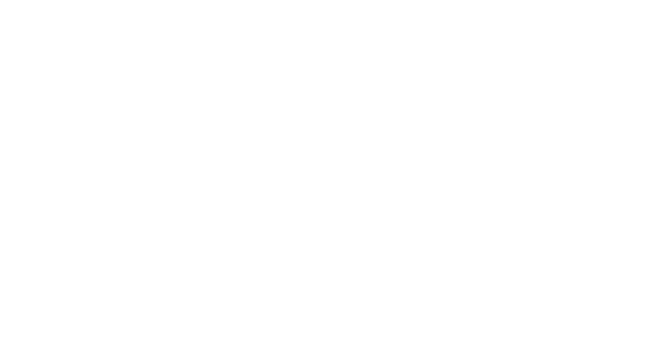 区分マンション投資とは?3つのメリットとリスク・予防策を解説2024-03-26コロナ禍を経て、不動産投資などの資産運用に目を向けられることが多くなりました。区......
区分マンション投資とは?3つのメリットとリスク・予防策を解説2024-03-26コロナ禍を経て、不動産投資などの資産運用に目を向けられることが多くなりました。区...... -
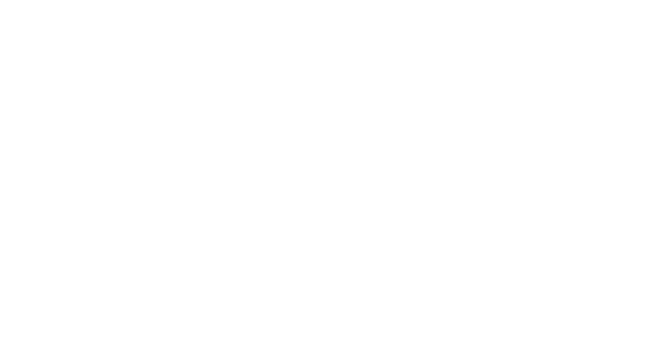 不動産投資に勉強が必要な理由とは?おすすめの学習方法7選を紹介2024-03-24不動産投資を検討している場合、効果的な勉強方法について知りたいと考える方も多いの......
不動産投資に勉強が必要な理由とは?おすすめの学習方法7選を紹介2024-03-24不動産投資を検討している場合、効果的な勉強方法について知りたいと考える方も多いの......


